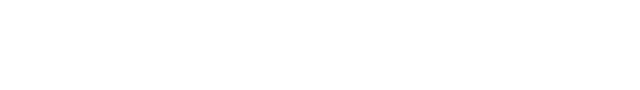性感染症外来
当院の性感染症外来の特徴
性感染症の種類は多岐に渡り、泌尿器科領域だけではなく、皮膚科領域の疾患も含まれます。
そのため、どちらの科を受診するか悩まれることも多いかと思います。
当院は泌尿器科と皮膚科両方の専門医である院長が両方の観点から診察を行いますので、安心してご来院ください。
症状がある場合、性感染症は基本的には保険診療が可能です。
症状はないが、心配で検査をしたい方はブライダルチェックをご利用ください。
クラミジア感染症
概要
クラミジア感染症は、クラミジアという細菌による性感染症で、男性尿道炎の主要な原因菌となります。
多くの場合、症状はあっても軽いのが特徴です。
症状
潜伏期間:1~3週間
- 尿道炎: 尿道から膿のような分泌物が出たり、排尿時に痛みを感じることがあります。しかし、症状がない場合も多く、気づかないうちに感染が広がることがあります。女性の場合、頻尿や排尿時の違和感、下腹部痛、おりものの増加などがみられることがあります。
- 精巣上体炎: クラミジアが精巣上体に感染すると、精巣の腫れや痛みが出ることがあります。放置すると不妊の原因になることもあります。
- 咽頭感染: クラミジアはオーラルセックスによって、のどに感染することがあります。多くの場合症状はありませんが、のどの痛みや違和感を感じることがあります。
原因と診断
クラミジア感染症は、主に性行為によって感染します。感染者との性行為で、粘膜を通じて細菌が侵入します。
診断は、尿検査、咽頭ぬぐい液検査などで、クラミジアの遺伝子を検出する核酸増幅法(PCR法など)が用いられます。
※咽頭の検査は自費検査になります。
治療法
クラミジア感染症の治療には、抗菌薬が使われます。
主に、マクロライド系(アジスロマイシン、クラリスロマイシン)やテトラサイクリン系(ミノサイクリン、ドキシサイクリン)、ニューキノロン系(レボフロキサシン)の薬が用いられます。アジスロマイシンは1回のみの服用で治療できるためよく使用されます。
薬をきちんと飲めば、多くの場合治癒が期待できますが、治癒率は100%でないため、治癒確認のため約3週間後に再度検査をして、完全に治ったかを確認します。
淋菌感染症
概要
淋菌感染症は、淋菌という細菌による性感染症です。
男性ではクラミジアと並び尿道炎の主要な細菌であり、クラミジアと比較して症状が強いのが特徴です。
女性では子宮頸管炎などを引き起こします。
症状
潜伏期間:3~7日
- 尿道炎: 尿道から膿のような分泌物が出たり、排尿時に強い痛みを感じることがあります。淋菌による尿道炎は、クラミジアによる尿道炎よりも症状が強く出ることが多いです。
- 咽頭感染: 淋菌は、オーラルセックスによって、のどに感染することがあります。のどの痛みや違和感を感じることがあります。放置すると、扁桃炎や咽頭炎を引き起こすこともあります。
原因と診断
淋菌感染症は、主に性行為によって感染します。感染者との性行為で、粘膜を通じて細菌が侵入します。
診断は、尿道分泌物や咽頭ぬぐい液検査などから、淋菌を検出する核酸増幅法(PCR法など)が用いられます。
通常、淋菌とクラミジアを同時にPCR検査します。
※咽頭の検査は自費検査になります。
治療法
淋菌感染症の治療には、抗菌薬が使われます。
現在では、セフトリアキソンという注射薬が最も有効とされており、単回投与で治療が可能です。
内服薬では効果が乏しく、点滴治療が必要です。
非クラミジア性非淋菌性尿道炎
概要
非クラミジア性非淋菌性尿道炎(NGU)は、クラミジアや淋菌以外の細菌やウイルスなどが原因で起こる尿道炎です。
マイコプラズマが原因として多いです。
症状はクラミジア尿道炎に似ていることが多いですが、原因となる菌が異なるため、治療法も異なります。

症状
主な症状は、尿道からの分泌物や排尿時の軽い痛み、違和感です。症状は軽く、無症状のこともあります。
主な原因と診断方法
原因となる病原体は多岐にわたります。
- マイコプラズマ
- ウレアプラズマ
- トリコモナス
- アデノウイルス
- 単純ヘルペスウイルス
- その他:大腸菌などの一般細菌や、カンジダなどの真菌
診断のためには、まず尿検査で白血球が増加しているかを確認します。
次に、クラミジアや淋菌の検査を行い、陰性であることを確認します。
その後、原因と考えられる病原体の検査を行います。PCR法で、マイコプラズマやウレアプラズマなどの遺伝子を検出します。
しかし、原因が特定できない場合も多く、その場合は、原因不明の尿道炎として治療を行います。
※マイコプラズマ・ジェニタリウムの検査は保険適用ですが、ウレアプラズマの検査は自費となります。
治療法
原因となっている病原体によって異なります。
- マイコプラズマの場合: 従来、クラミジア感染症と同様にアジスロマイシンの内服が有効とされていましたが、近年アジスロマイシン耐性のマイコプラズマが増加しており問題となっています。ドキシサイクリンやシタフロキサシンなどの抗菌薬が用いられます。
- ウレアプラズマの場合: ドキシサイクリンなどが用いられます。
- トリコモナスの場合: メトロニダゾールが用いられます。
- 原因不明の場合: いずれかの抗生剤を試します。
治療後、約3週間後に再度検査をして、完全に治ったかを確認します。
パートナーの治療と注意点
淋菌、クラミジア、非クラミジア性非淋菌性尿道炎はパートナーも一緒に検査、治療することが重要です。
パートナーが治療しないと、再び感染してしまう可能性があります。
また、感染が確認されたら、症状がなくても必ず治療が必要です。
感染中は、性行為を避け、治療が終わるまで、性行為を控えることが大切です。
性器ヘルペス
概要
性器ヘルペスは、単純ヘルペスウイルスによる性感染症で、性器やその周辺に水疱や潰瘍ができます。
一度感染すると再発を繰り返すことがあります。
症状
- 初感染: 初めて感染した場合、感染後2~10日程度で、外陰部や肛門周辺に小さな水疱が多発します。水疱は破れて潰瘍になり、強い痛みを伴います。初感染の場合、症状が重くなることが多く、発熱やリンパ節の腫れを伴うこともあります。女性の場合、排尿痛が強く、歩行困難になることもあります。
- 再発: 一度感染すると、ウイルスは神経に潜伏し、免疫力が低下すると再発することがあります。再発の症状は、初感染に比べて軽いことが多いですが、水疱や潰瘍ができ、痛みや違和感を感じることがあります。再発の前兆として、外陰部の違和感や神経痛のような痛みを感じることがあります。
原因と診断
性器ヘルペスは、性行為によって感染します。感染者との性行為で、粘膜を通じてウイルスが侵入します。
診断は、水疱や潰瘍の見た目で判断することが多いですが、近年は水疱の内容物を検査し抗原の有無を調べる迅速検査が出来るようになりました。
治療法
性器ヘルペスの治療には、抗ヘルペスウイルス薬の内服が行われます。アシクロビル、バラシクロビル、ファムシクロビルなどの薬を内服します。症状が出現したらなるべく早く治療を開始することがポイントです。
そのため年3回以上再発し、自分で再発の症状を判断できる方にはあらかじめ再発分を処方することが可能になりました。
また年6回以上繰り返すような方には再発抑制療法と言って一定期間バラシクロビルを連日内服することで、再発自体を起こらないようにする治療方法もあります。
尖圭コンジローマ
概要
尖圭コンジローマは、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染によって、性器や肛門の周りにイボができる病気です。
症状
尖圭コンジローマの症状は、性器や肛門の周りにできるイボです。
イボは小さく、柔らかく、鶏のトサカやカリフラワーのような形をしています。
色は、ピンク色や白色であることが多いです。
痛みやかゆみを感じることは少ないですが、放置すると大きくなったり、数が増えたりすることがあります。
原因と鑑別診断
尖圭コンジローマは、主に性行為によって感染します。感染者との性行為で、皮膚の小さな傷からウイルスが侵入します。
尖圭コンジローマの原因となるHPVは、主に6型と11型です。16型も原因となる場合があります。
鑑別が必要な疾患としては、梅毒の扁平コンジローマ、伝染性軟属腫、Bowen様丘疹症などがあります。
男性の場合、生理的な症状である真珠様陰茎小丘疹と間違えられることもよくあります。
治療法
尖圭コンジローマの治療方法には以下のようなものがあります。
どの治療法を選択するかは、イボの大きさや数、場所によって異なります。
いずれも単独では治 癒率が60~90%,再発率が20~30%であるために,複数の治療法を繰り返さなければならないことがあります。
液体窒素療法
液体窒素を浸した綿棒で疣贅を数秒間押し当てて凍結させ、壊死させる治療法です。1~2週間ごとに繰り返します。泌尿器科のみのクリニックの場合、液体窒素が出来ない場合がありますが、当院では可能です。小さなイボに適しており、痛みも軽度で治療の負担が少ない点が利点です。大きなイボの場合は治療に時間を要する場合があります。

ベセルナクリーム(イミキモド5%クリーム)
イミキモドを主成分とするクリームを外用する治療法です。患部に隔日で週3回塗布し、6~10時間後に洗い流します。広範囲、ある程度大きなイボにも適しています。塗布部位の赤み、かぶれなどの副作用が高頻度に見られます。効果が出るまで時間を要します。液体窒素療法と併用することも多いです。
電気焼灼
電気メスを用いて外科的に疣贅を焼灼する治療法です。外科的治療のため、比較的短期間で効果が期待できますが、組織傷害が深く、瘢痕が残る可能性があります。またコンジローマはウイルス感染症のため、肉眼的には取り切れていても、治療後に再発する場合もあります。
梅毒
概要
梅毒は、梅毒トレポネーマという細菌による性感染症で、全身に様々な症状が現れることがあります。
最近、患者数が増加しています。
症状
梅毒の症状は、感染からの期間によって変化します。
- 第1期: 感染後10日~3週間程度で、性器に硬いしこり(初期硬結)ができ、それが潰瘍(下疳)になることがあります。しかし、痛みなどの自覚症状がないことが多いです。
- 第2期: 感染後3ヶ月程度で、全身に発疹が出ることがあります。発疹は、赤い斑点や丘疹、膿疱など、様々な形をしています。手のひらや足の裏にも発疹が出ることがあります。扁平コンジローマという、肛門や外陰部などにできる湿ったイボも、第2期梅毒に見られることがあります。その他、発熱や倦怠感、リンパ節の腫れ、脱毛などの症状が出ることもあります。
- 第3期: 第2期から数年経つと、皮膚や骨、内臓にゴムのような腫瘍(ゴム腫)ができることがあります。
- 第4期: さらに放置すると、心臓や神経に重篤な障害が出ることがあります。
原因と診断
梅毒は、主に性行為によって感染します。感染者との性行為(膣性交、肛門性交、オーラルセックス)で、粘膜を通じて細菌が侵入します。診断は血液検査で梅毒の抗体を調べる方法が用いられます。感染初期(4週以内)は血清反応が陰性の場合があるので注意が必要です。
治療法、治癒判定
梅毒の治療には、ペニシリン系の抗菌薬が使われます。ペニシリンアレルギーがある場合は、他の抗菌薬が使われます。薬を4週間内服すると、ほとんどの場合治癒を期待できます。治療後も定期的に血液検査を行い、抗体値の減少を確認する必要があります。