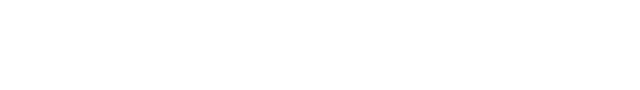亀頭包皮炎
亀頭包皮炎とは
亀頭とそれを覆う包皮に炎症が生じる疾患です。悩まれている方も多く、当院でも数多くの方が来院されます。
かゆみ、痛み、赤み、腫れといった不快な症状を引き起こし、日常生活に支障をきたすこともあります。
亀頭包皮炎は細菌やカンジダ、ウイルス感染によるものなど原因が多岐にわたります。
そのため正確な診断をしたうえで原因に応じた適切な治療をする必要があります。
皮膚科、泌尿器科どちらに行くべきなのか悩まれる方も多いですが、当院では皮膚科と泌尿器科両方の専門医である院長が診察致しますのでご安心ください。
症状
亀頭包皮炎の主な症状は、亀頭と包皮の炎症に伴うものです。
陰部の赤み、腫れ、痒み、亀頭と包皮の間から白いカスのようなものや膿が分泌されることがあります。
症状の程度は、軽度なものから重度なものまで様々であり、原因によって症状の現れ方にも違いがあります。
細菌性亀頭包皮炎は比較的症状が強く、赤みや腫れが強い傾向にあります。
一方、カンジダ性亀頭包皮炎は皮むけや白いカスが溜まることが多いです。
原因
亀頭包皮炎の原因は以下のものが挙げられます。
細菌性の亀頭包皮炎が頻度としては多いですが、原因が混在していることもあります。
細菌感染:
大腸菌やブドウ球菌、連鎖球菌などの常在菌や、外部から侵入した細菌が、陰茎の小さな傷などから感染し、炎症を引き起します。不潔な環境や性交渉など強い刺激も細菌感染のきっかけとなることがあります。
真菌(カビ)感染:
カンジダという真菌(カビの一種)が原因となることが多く、特にカンジダ性亀頭包皮炎として知られています。
カンジダは、健康な人の皮膚や粘膜にも存在する常在菌ですが、免疫力が低下している時や、陰部の環境が変化した時などに過剰に増殖し、炎症を引き起こすことがあります。
湿疹性 :
外部からの刺激や体質により陰部の皮膚が炎症起こし、赤みや痒み症状が出現します。
ウイルス感染:
性器ヘルペスなどのウイルス感染が亀頭包皮に炎症を起こします。
診断
亀頭包皮炎の診断は、亀頭と包皮の状態(赤み、腫れ、分泌物の有無、皮膚の変化など)を観察し、症状の程度を評価します。
原因検索のために培養検査や顕微鏡検査などを行います。
培養検査:
炎症を起こしている亀頭や包皮の表面を綿棒で拭い、採取した検体を培養することで、原因となっている細菌の種類を特定します。複数の細菌が検出されることもあります。
顕微鏡検査:
皮むけや白いカスを顕微鏡で検査し、カンジダの菌糸の有無を確認します。
尿検査:
尿中に細菌や白血球が含まれていないか、また尿糖の有無などを調べます。
尿道炎の合併や、糖尿病の可能性を確認するために行われます。
ウイルス検査:
性器ヘルペスが疑われる場合は、水疱の内容物やびらん部位を拭い取る検査を行います。
採血:
梅毒の合併を疑う場合は採血を行います。
治療
原因に応じた治療を選択することが重要です。細菌性の場合は抗菌薬の外用や内服を行います。
カンジダ性であれば抗真菌剤の外用を行います。湿疹性の要素があればステロイドの外用も行います。
様々な原因が混在していることも多く、一つ一つ治療していくことが大切です。
誘因と対策
亀頭包皮炎の誘因には以下が挙げられます。
誘因となるような行為を避け、繰り返さないように適切な対策をとります。
誘因
陰部の不潔:
包皮の内側は汚れが溜まりやすく、不衛生な状態が続くと細菌や真菌が繁殖し、炎症を引き起こすことがあります。
特に包茎の方は、亀頭と包皮の間に汚れが溜まりやすく、亀頭包皮炎を発症しやすい傾向があります。
機械的刺激:
性行為や自慰行為、きつい下着などによる過度な摩擦や刺激が、亀頭や包皮を傷つけ、炎症の原因となることがあります。
糖尿病:
糖尿病の方は、高血糖の状態が免疫力を低下させ、細菌や真菌の増殖を助けるため、亀頭包皮炎を発症しやすい傾向があります。
特に、尿に糖を排出するタイプの糖尿病治療薬を使用している場合、尿に糖が多く排出されるため、陰部が細菌や真菌の温床となりやすいことがあります。亀頭包皮炎を契機に糖尿病が発見されることもあります。
対策
清潔を保つ:
毎日、陰部をぬるま湯で優しく洗い、亀頭と包皮の間に溜まった汚れを丁寧に洗い流しましょう。
ただし洗いすぎは皮膚のバリア機能を低下させ症状を悪化させるため、注意が必要です。
通気性の良い下着の着用:
吸湿性・通気性の良い綿素材の下着を選び、締め付けの少ないものを選ぶようにしましょう。
刺激の回避:
化学物質や物理的な刺激は、亀頭包皮炎の症状を悪化させる可能性があります。過度な刺激は避けます。
糖尿病の管理:
糖尿病の方は、血糖値を適切に管理することが亀頭包皮炎の予防と治療に不可欠です。